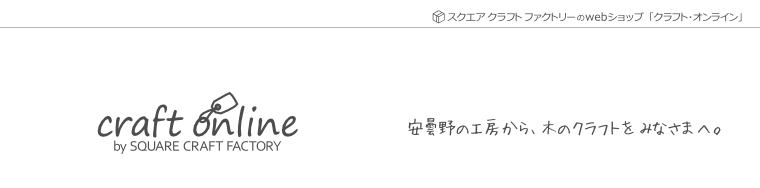|
木目の美しい材として知られています。
また、経年変化によって
紅褐色に変化していく性質があります。
蓄材量が限られていることもあって、
最近では、高値で取引される傾向にあります。
木質は、やや重硬とされていますが、
比重には、個体差があります。
加工性は、重いもの、軽いものも、非常に良好。
床の間、柱、内装、造作、装飾等の住宅用に、
楽器、家具材、彫刻材にも使用されます。
めずらしい用途としては
絵を描くときにつかう木炭の原材料や、
三味線の胴にも。
木は、秋になると、果実をつける果軸が、
徐々にふくらんで、甘くなります。
この果軸、酒につけて果酒を作れます。
そのままでも食べることができます。
煎じて飲むと、二日酔いに効くとされています。
この果軸の先に、実がつきます。
大きさは数ミリ程度で、
サルなど、哺乳類が食べます。
(人間は食べません)
果実には種が含まれるので、めでたく運ばれ、
ケンポナシは、子孫を残すことができます。
甘い果実をつける木であるためか、
材にも、甘い香りをまとっています。
ケンポナシの木は、
北海道の一部を除き、日本全国に分布。
ヒマラヤ山脈から中国、
朝鮮半島にも生育しています。
木は、まとまって生育することがなく、
森や林のなかに、ときおり一本だけ見かける、
いわゆる点生する傾向にあります。
気乾比重:0.55〜0.85
|

写真は、2014年8月、
長野県岡谷市、駒沢諏訪社にて撮影。
樹高が20メートル、胸高の太さが3.71メートル。
岡谷市の天然記念物に指定されています。
諏訪地方では、ケンポナシの木のほとんどが、
神社にて生育しています。
なぜ「ケンポナシ」と呼ばれるのでしょうか?
植物学者の牧野富太郎は
「テンボウナシ(手棒梨)の転訛とし、
玄圃梨と表記するのは間違いであろう」
としています。
「手棒梨」は「手」に「棒」を握った、
その姿に似た「梨」のような実がつく、
ということで、手棒梨。
昔はテンボノナシとも呼ばれ、それが
ケンポコナシ→ケンポノナシ→ケンポナシ
と転じていった、ともされている。
かつて、日本人が、南米に移住した際、
このケンポナシの木を持って行ったそうで。
ブラジル名は「uva
japones=日本人の葡萄」
と呼ばれています。
実は薬に、木は木工材料にと、
とても、重宝する木だったことがわかります。
(バラ目・クロウメモドキ科・ケンポナシ属)
|